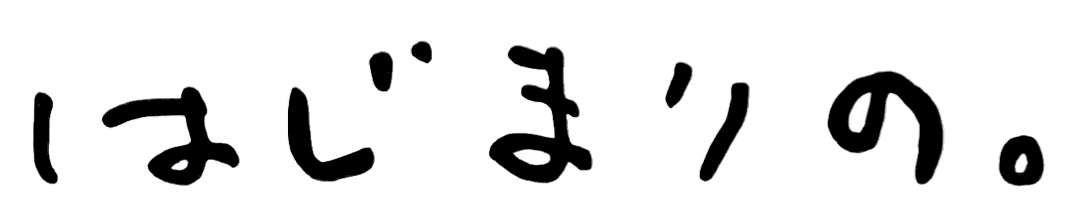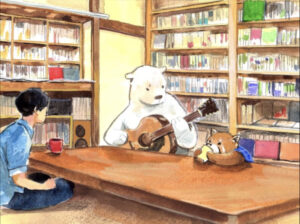京都・出町柳にある『山食音』は、その名の通り、“山、食べること、音楽”を取り扱うショップ。一見、何の繋がりもないそれらはいずれも店主の東岳志さんのライフワークになっている3要素。子供の頃から山を嗜み、出掛けるときは辞書を持ち歩き、疑問に思ったことはすぐに調べるほど好奇心旺盛だったという東さん。坂本龍一や細野晴臣、青葉市子などのレコーディングエンジニアとして活躍する中で“いい音を録るには体を整えることが必要”と考え、食について追究することが始まったといいます。東さんが『山食音』を開くことになった経緯について、その独自の視点を追いながら話を聞きました。
――もともとレコーディングエンジニアだった東さんが個人の趣味で南インドのミールス作りにハマり、それを東京・吉祥寺にある『キチム』で提供することがお店を始めるきっかけだったそうですね?
東 そう。その頃はまだ自分の店はやってなくて。いつも家で作って食べてるセットを試しに出して、何人か来てくれたお客さんも「美味しい」と言ってくれて、そのとき遊びに来てくれてた原田郁子さん(3人組バンド・クラムボンのp&vo)も「美味しい」と言ってくれて。
――原田さんとはどういう経緯で知り合ったんですか?
東 最初は元・立誠小学校で郁子さんが2daysのライブをやったときがあったんだけど、その公演の前日か前々日に“無指向性スピーカー(十二面体スピーカー)を探してる”ってことで連絡をもらって。で、sonihouse(奈良のスピーカーメイカー)の鶴林万平さんを紹介したら急な申し出だったこともあって「2日目は来れるけど、1日目は無理」と言われて。じゃあ、2日目だけでもお願いしますと。で、そのときのライブを話の流れからサラウンド録音をすることになって……zAkさん(フィッシュマンズ、BOREDOMS、クラムボンなどを担当してきたサウンドエンジニア)と僕で、ピアノの真上に4チャンネルをセットして収録したんですね。郁子さんとはそこで初めてしゃべった感じで、それまでは何となく知ってるみたいな。
――なるほど。ちなみにミールスの出会いはどこやったんですか? インドで?
東 いやいや、最初にミールスのことを知ったのは東京の南インド料理屋なんですけど、そこから時間が経ってもなんかミールスのことがずっと記憶にあって。で、大阪の『チョーク』さんがミールスをやってるという話を聞いて、すぐに行ってみたら、まだオープンして半年くらいしか経ってないのに大ファンの人がたくさんいて。そこから本当に毎週のように仕事帰りに行くほど楽しみになって、そのうちに自分でも作るようになったというか。で、しばらく経った頃に大阪の『カレー茶竹馬』とか『谷口カレー』が“カレー会”というものをひっそり作っていて、ちょうど自分もカレー作りにハマってたときだったので、カレー会にもしかしてネパール料理で参加できるかもなと思ったりして。

――その後に京都の『タルカ』でも働き始めるんですか?
東 それはもっと最近で、『タルカ』が人が足りんってことで1日くらいなら手伝いますみたいな。
――どこかでいろいろお店で働いて、自分の味を探していった感じなんですか?
東 いや、働いて探してはないかな。日常的に食べてる中でレシピがもう出来てたから。
――もともとレコーディングエンジニアとして仕事をする傍ら、週末だけ食堂を『PLANT LAB.』という名前で開いていましたよね。家で作ってるミールスを『キチム』で提供して、それが評判だったということで、その延長上で『PLANT LAB.』をやることになったんですか?
東 うん、その延長。『キチム』の翌年の3月くらいに、京都のちぃこさんという人から「前に料理したい。料理できるところ探してると言ってなかった? 週末だったら貸せるんだけど」と聞かれて“じゃあ、やります”と答えて、その週末からPLANT LAB.を始めて。
――即答だったんですね。
東 まあ、やってみないと合うかどうかもわからないから。とりあえず1週間やってみて、それでどうなるかな?みたいな。
――間借り&週末営業だった『PLANT LAB.』を経て、現在は『山食音』を経営されているわけですが。『山食音』はご自身では何屋さんだと思いますか?
東 それはもう山食音でしかないから難しい。ベースは食堂かな。
――登山のULブランドの“山と道”と一緒にお店を開くことになったのはどういう経緯だったんですか?
東 まあ、成り行きでなったというのが正直なところで。僕は店舗を作るのはまだ早いと思っていて、ただ早いと言ってたら一生できないというのもあって……みたいに考えていたタイミングで、山と道の夏目さんが声を掛けてくれて、それが熱烈アピールで。

――夏目さんからのラブコールを受けて『山食音』をオープンすることになったと。
東 ラブコールに負けたという。
――夏目さんは鎌倉以外に関西にも拠点が欲しかった感じなんですか?
東 関西だけじゃなくて全国に欲しいと思っていたみたい。で、山道具の説明ができる人がよくて、ショップじゃない人がいいっていうのはあったみたいで。
――ショップというと“物を売る販売員”じゃなくてということ?
東 そう。物を売る人は物しか売らないから。
――価値を売る人であってほしいということですか? 価値を見出す人というか。
東 まあ、自分のところを贔屓してほしいというか。山と道の良さを本当に伝えてほしかったんだと。
――なるほどね。夏目さんとはどうやって知り合ったんですか?
東 ネットで(笑)。お互いに存在を一方的に知っていて。僕については“料理を作る変な名前の人”という認識だったと思う。“電気くん” (東さんのあだ名)という名前で、なんか料理をやってて音楽もやってるらしいみたいな感じで知ってもらったというか。
――なるほど。そもそもですが、東さんの本業は音楽のレコーディングエンジニアですよね? エンジニアの師匠となるとzAkさんになるんですか?
東 いやー、師匠というか、影響を受けて考え方が変わった人は何人かいるけど、zAkさんはそのうちの一人というか。技術的なことは学んでるようで学んでないというか。直接、“こういうふうにするねんで”と教えてもらうことはなくて、見て盗むみたいな感じでした。zAkさんは考え方が自分と近いなとは思ってるけど。なので、自分にとっての師匠は特にいないです。
――エンジニアとしての修行はどこかでしたんですか?
東 いや、やってない。すべて自己流でやってきてるから全部がエセ。
――いやいや(笑)。じゃあ、機材とかも自分でトライアンドエラーで試していって?
東 そう。“これがいいかな”と思うものを試して、怪しみながらも、よかったら最後まで録るっていう。

――そういえば東さん、以前「道端に生えている雑草を全部食べて試した」と言ってませんでしたっけ?_(笑)
東 全部じゃないけど(笑)。気になって食べられそうなヤツはとりあえず食べたかな。あとはサプリだけで暮らしてたりとかもしてましたよ。
――え、サプリだけで!?
東 全然暮らせますよ(笑)。
――そうなんですか。もともと食に興味はなかったんですか?
東 いやいや、サプリに興味があったから。
――ハハハ(笑)。
東 はっきり言ってサプリだけで暮らせたら何の苦労もないなと思って。毎日食べたいものを悩む必要もないし。
――確かに、合理的ですよね。
東 まあ、サプリだけって言うと嘘になるかな。家の中ではサプリしか食わない。外食はちょこちょこ仕事先で食べるけど、その他は全部サプリ!
――それは身体、悪くなったりしないんですか?
東 めっちゃ元気!
――ハハハ(笑)。
東 身体が軽いし、脳内もスッキリするし。ただ、食べたくなる欲求がどんどん溜まっていって、その欲求を振り払うのが大変で。でも、食べなくてよくなって、それが1週間くらいのプチ断食をするきっかけになって。
――それは今もやるんですか?
東 断食は今はあんまり。身体が疲れたらするかな。でも断食せなあかんってことは何か悪いものを食べてるってことやから。食べる断食っていうか、結局何も身体に蓄積させないほうがいいかなと考えるようになって。ちょうどいい量を食べ続ければ、断食をする必要はないと思ってて。で、1日寝る時が内蔵を休める時やから、寝る前に食べないとか。それを本当にすれば、たぶん自然と健康になるから。
――勉強になります。ちなみに、東さんって“まずは自分の感覚でやってみよう!”という気持ちが強いんですか?
東 やってみようというか、やってみてから考えようみたいな感じかな。
――これまで過去にプロスキーヤー、お笑い芸人、建築家なども目指されていたということですが、それも自分に合うものをやってみて考えようという感じで?
東 あ、建築家は目指してないですよ。過去に建築事務所に入ったことはあるけどそれだけで。実際、建築事務所にいても“大工さんと1対1でやるセルフビルドな建築”って少ないんですよ……まあ、今でこそ、そういうやり方で施工するのも増えてきてるけど、ほとんどが業者のサンプルを組み合わせて効率内で収める仕事で。“こういう夢のない世界では、巨大化を図って自分の名前を売る以外ないのか”と思うと、登山家以上におもしろくないと思って興味が失せたので。
――ということは、登山家もあまり夢がないと思ったんですか?
東 登山家も正直、海外にお金かけて行って登る山があれかと。自分にとっておもしろい山って白紙のフィールドというか“完全に未知なところに行きたい”って願望で。それで昔はヒマラヤとかアルプスに行きたいとは思ってたけど、山を取り巻く具体的な状況が少しずつ見えてくると“なんや”と。単純に日本のアルプスに行って、その次が世界の山を目指すことになるんだろう、そのために山岳会みたいなものに入って、人間付き合いもあって……となると、それってやりたいこととやっぱり違うなと。それやったら他の人間付き合いのほうがいいし、すべて面倒に思えて。で、今は週一しか山に行けてない現状ではあるけど、理想的なんですよね。日常的にできる山を探してたんで、大文字山に行くのがライフワークになってて。
――『山食音』では不定期にワークショップもされていますが、“まずはやってみて、自分の感覚で自分のやり方を見つけてもらおう”みたいな気持ちがあるんですか?
東 まあ、みんな同じ遊び方になるでしょ? 「どこ行きましたか?」と言ったら、大体が六甲山とかで。中には日本アルプスがあって“あ、そうですか”と。山登り始めは富士山とか。
――屋久島とかですね。
東 “みんな、同じ遊び方やからいい”みたいな……歌謡曲とかも、同じ曲を聴くってことは同じ会話ができるきっかけだと思うんですけど、山好きやったら同じ世代は“そこの山行った、行った”みたいに話せる。それはいいと思うけど、その世界が好きやったらもうちょっと深く越えてもいいかなと。深くっていうか、自分で見つけられる人が増えたらいいなと。
――なるほど。ちなみに『山食音』では山と道の用品を取り扱い、ミールスも販売されていますが、音は何か取り扱いが増える予定なんでしょうか?
東 “音”という文字は、今後、僕がレコーディングとか何かしらやると思うので、それを肩書きで入れたらいいかなと思って。
――普段からいろんな場所でフィールドレコーディングもされてますもんね。
東 フィールドレコーディングはライフワークみたいなもんなんで(笑)。

――ちなみに以前、「レコーディングする時に、自分の耳がつねに一定じゃないといけない。だから身体を整えないといけないし、食事にも気をつけないと」と仰って増田よね?
東 それは絶対そうで。どう考えても耳の聴こえ方って、精神状態とかによって変わるし。お酒を飲んでたりしたら気持ちよく聴こえちゃうし。自分の状況によって聴こえる音が変わるというのは、リスナーとしては全然いいけど、音を操る側としてはちょっと頂けないんじゃないかなと。そういうことは気をつけたいなと。
――レコーディングする時って自分の感性は大事じゃないですか? と同時に、感性に浸りすぎてもダメですよね。冷静でないとダメみたいな。そこってどういうバランス感覚を意識してレコーディングされているんですか?
東 練習しかないかな。そんなことは考えない。山登る時とかに自分の右足の出し方とか考えないで、結局、普段登りたいなと思ってる登り方ができてる体験をいかに増やすか。だから、こういう角度で録ってみたらっていう体験をいかに増やして、それが本番で出るんですよ。だから、フィールドレコーディングをどんどんやらないと、本番パッと出た時に思った位置に置けない。だから、たまにスタジオで録音する人は思った位置に置けてるはずがないんです。その場で考えてる。それは身体の神経反応で出てるマイキングじゃないから、嘘というか、その人のものじゃないから。極論を言ってみると。
――言葉もそういうところがあるんですけど、自分の頭の中で思ってることと言葉としてアウトプットする時に、距離だったり隔たりが練習してないとあって。うまく言葉出てこないみたいな。
東 だから、日常的にやってることはペラペラしゃべられる。だけど、日常的にやってない自信がないことは、探しながらしゃべるから、やっぱりベラベラしゃべられない。それは録音とか、歩くこととか、作ることとかも、日常が最大限力で、そこにどう落とし込むかってところが、その人のすべてというか。だから、日常的にきちんとするクセをつけろっていうのはそういうことで、丁寧にやってると丁寧なクセが出ちゃう。
――すべて日常の延長ということですね。
東 そう。しゃべってる今も日常なんですよ。だから、すべて流れの中に流れがある感覚というか。そういうのがわかってるけど、できなかったことが……ここ何年かですごいクリアに見えてきてるのが30代に入ってからすごいおもしろいですね。